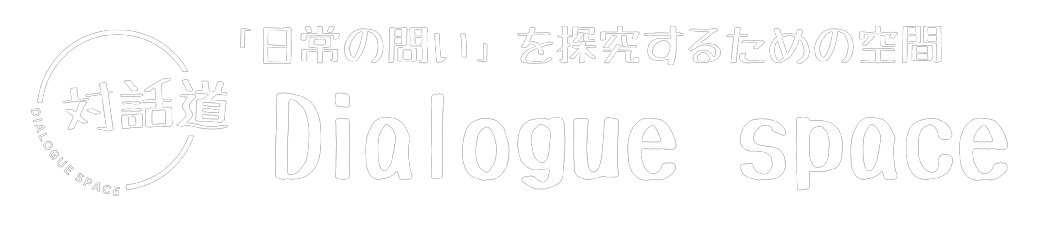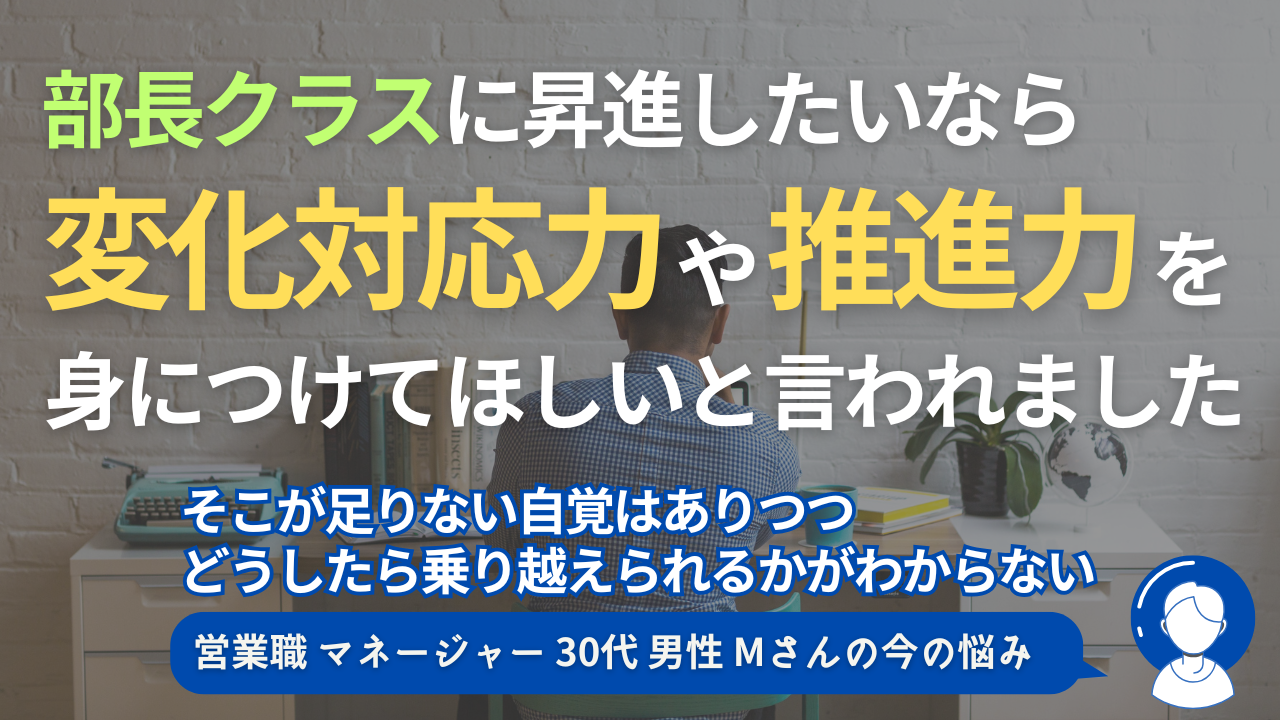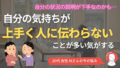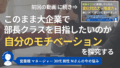動画で見る
記事で読む
今後のキャリアについて悩んでいます

えっとですね、この4月に育児休暇から、復職しました。で、戻ってきたらですね、まあ部署的に、赤字になっているということもあり、だいぶ様子が様変わりしていました。まず人が半分に減っていたりとか、他にもいろいろこまごましたのはあるのですけど……というのが、事業の状態としてありまして。
で、ちょうど先週に部長と面談があったんですよ。で、「これからキャリアどうしたいの?」みたいな話をしている中で、私に対してのフィードバックとかいろいろいただいたんですけど。ちょっとそこが自分の認識でも、確かにそうだなっていうものをいたいたんですが、それって逆にどうやって乗り越えればいいのだろうかというのが、逆にちょっと分からないフィードバックでして。
ただまあ、自分としては自覚は結構あるので、これはどうしたものかというのと。ただ、それを(その場で上司に)会社的にオープンに会話して、何かプラスに働くイメージも持てなかったので、社外の方とお話しさせてもらって、ちょっと整理だったりとか、自己認識深めていければなと思っているという、そんな感じです。
なるほどです。そしたら、一旦差し支えない範囲で、その上司の方とどんな話をされたのか、教えてもらっていいですか?

半期に1度ですね、管理職の人が自分の配下にいるメンバーの昇格とか異動とか、評価とかを考える会議が、そろそろ近づいていますねと。という中で、「どうしたいか教えてほしい」という話だったんです。
それに対して、僕は、「部長として、機会があれば頑張りたいです」という話をさせてもらって。で、それが難しいんだったら、営業以外の現場でスキルを広げるチャレンジがしたいですという話をさせてもらったんですね。そのときに言われたのが、まず会社的には、結構まあどの会社もそうですけど、変革期というか、今ある事業を変えていかないとですねというフェーズにおいて、そういう変化対応力みたいなものが求められていると。そこの部分については、ちょっと物足りないみたいなフィードバックだったんですよ。
それ以外の基本的な能力に関しては、そんなに問題があるわけでもなく、まあ信頼はしているし、一定の評価はちゃんとしているよということを言っていただいて。(上司は)そんなおべっかを使うようなタイプではないので、そこはそうなんだろうなと思いつつ、変化対応力みたいなところとか、あと、なんて言うんですかね……言われたのが、「どんどん自分で何か決めて、巻き込んでいけ」みたいなことを言われたんです。としたときに、なんて言うんですかね……こう、自分でこう旗を立てて、例えば「これをやるんだ」とか、「これがやりたい」というものが、(正直)あまりないんですよね。だったときに、え、これってどうやって突破すればいいんだろうというのがちょっと分からなくて。
なんか単純に、例えば、論理的思考能力が足りないとか、コミュニケーション能力が足りないとか、スキルの話なのであれば、まだやりようがあったと思うんですけど、自分で何か旗を立てて、そこに向けて決めて動いていくとか、それに向けて、巻き込まれる側ではなくて、自分で巻き込んでいく側として何かを変えていくとかっていう話をされたときに、うん、これは、どうやって乗り越えればいいのかというのと、果たして、そもそも自分がそういうことってやりたいんだっけ?というのが、ちょっと分からなくなり、迷子になっているというのが現状です。
いやあ、なるほどです。なんかそれは迷子になるのは、もう致し方ないですし、だいぶ大転換ですよね。
「こうすればうまくいくんだ」「世界がこうなんだから、この世界の中でどうしたらうまくいくか」という外側にどう合わせるかという世界から、自分は「世界をどうしたいのか」、「その世界をどう変えたいか」という内発的にビジョンを描いて自分で決めて人を巻き込んで動くという世界は、全然違いますからね。もう本当に真逆ですよね。それは迷子になるのは当然の話ですというのは、まあ、大前提なのですけど。
「じゃあ、どうしたらいいんですか」のヒントが欲しいという意味で言うと、すごくいろいろありますが、1つは、やっぱりこれまでの人生を振り返って、自分って何が本当に楽しかったのかなとか、嬉しかったのかなとか、喜びを感じたのかなというのは、ヒントになるはずというのが、一旦私からの回答です。

確かに、その観点は全くなかったので、確かに……改めてそこはやってみたいなというのと。あと、なんか一方で思ったのが、管理職をやっていて、ヒトかコトかでいったら、社内的にはヒトよりコト側の方が得意だよねという、認知はされているのでうすが、ただまあ、自分自身がやっていて楽しいのは、人とか組織とか、そっちの方だったりするんですよね。何が楽しかったかなで言うと、人・組織周りのことをやっているときが、思い返すと面白かったなっていうのが、まずあります。
で、悩ましいのが、今、新規事業っぽいところにいるので、最早そんな話が事業的に出てこないんですよね。まあ、出てくるんですけど、なんかもう「人のモチベーションが」とか言ったら、事業が前に進まないみたいなところがあるので、ヒトよりコトの話に、結構なっているというのと。私自身が、ちょっと今の事業に対して、あまりこう…希望を持てていないみたいなところは正直あるので、その中で「こうしたい」とかっていうのが、なかなか、出てこないというのが悩みですかね。まあもうちょっと、内省は、いただいたアドバイスでちょっとしてみたいなとは思うんですけど。
人・組織をモチベーションに事業を頑張るという考え方もある
でも、今のセリフだけとってみても、自分としては楽しいのは、人・組織系の方だという話だったときに、本当に究極モチベーションを根本におけたら、人・組織をモチベーションにしながら、事業開発の話とかもできるといえばできるんですよね。
何を言っているかと言うと、私は、組織づくりの支援みたいなことをずっとしてきているんですけど、ちょっとあえて分かりやすく言うと、「金儲けしたいんです」という社長さんがいて、「金儲けするために、いい組織にしたいんです」と、言われたとします。で、私は「いい組織を作りたくて、そのためにはお金も必要です」みたいな感じなのですけど、これって実は噛み合うんです。
金儲けするために、お金のある会社が私に発注してくれて、組織づくりを頼んでくれる。で、私は素晴らしい組織づくりをして、その会社が儲かるようにするとしたら、WinWinというか。そして、また儲かったお金で私にもう1回発注してもらって、さらにいい組織にしてみたいな……まあそんな感じで、私で言うと、コンサルタントみたいなポジションだからやってきたわけですね。
で、これを、じゃあ、社内の事業責任者としてやる。「自分がやりたいのは、本当はいい組織を作りたいというところで、儲けたいわけじゃないんだ」という人でも、でも、儲かっていなかったら社員を雇えません。社員を雇いつつ、自分が雇っているメンバーを「本当にこのチームで働けてよかった」って持っていく。そのためにも稼がなきゃいけない、みたいなふうにしていくというのは、まあ、1つできるんじゃないかなって思うんですけど、今のを聞いてどうですかね?

なんか、おっしゃられることは確かにそうだなと思っていて。ただ、ちょっと現実、なんか突破口が見いだせないみたいな状態だなと感じています。今、すごい部署のコンディションが悪くなっているのは、ひたすら新しいお客さんを取らなきゃいけないというのが、至上命題になっていまして。これまでは、ちゃんとお客さんの採用の成功支援とかっていうこともやっていたんですけど、なんか、突然「電話の新規開拓だ」みたいな、めちゃくちゃ振り切ったんです。で、その電話がけが、大体アポが取れる率が、100件かけたら1~2件ぐらいの世界観のリストを渡されていて、なんか、もうどんどん、みるみるみんな元気がなくなっていきます、みたいな状態なんです。
でも、そこを突破しないと、結局、売上が立たないので、より人が減らされたり、事業を畳まなきゃいけないよねというので、私の上司も、横のマネージャーとかも、なんかもう「四の五の言わず、やらなきゃいけないんじゃない」という空気になっており。それをこう……うまく突破できる……、なんて言うのかな、他の手段がちょっと思いついていなくて、みんなで、苦しい戦いをしているみたいな感じだったりするので。そんな中で、組織のこととか一切考えなくなってしまっていたなと思いました。
部長や経営陣クラスを目指すなら考えないといけないところ
もしMさんが今、独立をして、自分のお金で法人を立ち上げて、社員も雇って……ということをしたら、社員に約束したお給料を払うために、もしも赤字だったら、死ぬほど働くしかないですよね。自分で雇って、自分でそのお給料を払うことを約束していますから。
この感覚って、本当に起業家にならないと正直難しいんですけど、でも部長や経営陣に求められるところとして、1つこの感覚で仕事に取り組んでいるかというのはあると思います。
その感覚を持てたら、今いる会社の中でより活躍できてもいいですし、もう何なら起業して今の会社を出ていってもいいんじゃないかなというのは思いますね。

それは、立場とか関係なく、もうとにかく稼ぐのであるという話ですか?
自分のためにも、部下のためにも。だって、給料を払うために稼げなければいけませんから。
組織というものは、給料を払えないところには、基本的にほぼ成り立ちません。NPOとか、ボランティア団体とか、給料を払っていなくても人が集まってくるような組織もあるにはありますけど、でも結局NPOみたいな組織も、ちゃんと必要なだけの支払いができていないNPOは、人は離れていくんです。だから、やはり、いかにちゃんとお給料を払ってあげられるように稼ぐかというのは、上位役職者になればなるほど、すごいあるかと思いますね。

いや、そこまでのマインド、全然持てていないですね。なんか会社員という感じのあれになっちゃっています。もちろん、(そんな状態の自分を)いいとは思っていないんですけど、なかなか変われないというか……甘えています。
部長になるとか、事業部長になるとなったら、やはりそこがないとできないですよね。

うん。いやいや、最初のところに戻ってきましたね。いや、でも、そういうことなんだろうなという。ってなったときに、そこの姿勢というか、「何が何でもやるんだ」みたいなのが、うーん、まあ現時点では正直、持てていないみたいな、現状があって。
で、そうですね、「部長やってみたい」みたいなのも、なんか部長になって何か具体的にやりたいことがあるというよりは、経験として、スキルとして、ちょっとやってみたいというぐらいだったりするので。そうですね、その状態だと、やっぱり、もう一段、もう一皮むけないといけないんだなというのは、頭で感じつつ。この一皮むけるは、スキルの話でもないのかなって現状捉えているので、より、なんて言うんですかね……突破口が見えないというか、逆にどうしたらいいんだろうかというのが今の悩みですね。
ちょっと寄り添わない回答になってしまうのですけど、これはスキルと言えばスキルなんです。部長スキル、事業部長スキルなんですよ。事業部長のポジションにつきたいのであれば、そのスキルが必要なんです。
でも、「スキルじゃないな」という風な表現が出てくるのも、すごい分かります。自分以外の面倒を見るという覚悟ですからね。自分のキャリアのために、を超えていますから。みんなを食わせてあげたいとか、みんなを幸せにしたいってならないと、やはりできないですね。

いや、そうですね。その覚悟みたいなのが、多分、一番、なんて言うんですか……それだなという風に、単語としては、腹落ちしたんですけど。うーん、なんか、そこまで責任をこう、まだ持ち切れていないという部分がありますね。うん、ありますね。
なので、部長から言われたときも、例えば、新規事業なこともあって、いろいろ議論して決めるというのが日常茶飯事なんですけど、なんか「喋ったらちゃんと意見とか出てきて、割とまともなことを言うのにな」、それを何が何でも通すとか、人とぶつかってでもしっかり議論するとかってなった瞬間に、「急にその他大勢のマネージャーと一緒だな、お前は」と言われたんですよ。
それもいろいろ考えたときに、私は、今日この場で石川さんと話すまでは、事業に対しての「こうしたい」ということがあまりないので、それが出てこなかったんじゃないかなと思っていたんですけど、一旦、覚悟を、先に持つというか、みたいなことが、必要なのかなというのを、なんとなく今の会話で、自分の中で整理し直してみたという感じです。
外に向かう人と内に向かう人 どちらも事業を広げる
これはタイプとして、外に向く人と内に向く人っているんです。
一定ラインまできたときに、「社会をこうしたい。だから、事業を通して社会を変えられる事業をこうやって作っていくんだ」ということに情熱が向く人もいます。いや、「一緒に働いてきたメンバーを輝かしたい」「この人たちを輝かすフィールドを作りたい」と、内側に向く人もいます。どっちも結局、事業を作っていくのです。
どっちも結局、事業を作っていくときに、どっちがモチベーションでも、私はいいと思っているのですけど、さっきの話を聞いて、Mさんは、「社会をこうしたい」よりは、「メンバーを輝かしたい」みたいな方が頑張れるんじゃないかと思いました。

あ、そうですね。そこは、おっしゃる通りですし、そこのモチベーションはあります。そう考えたときに、例えば、あくまで会社でやっている事業やサービスは、外のお客さんのために、基本存在するじゃないですか。なので、お客さんがいて、まあ世の中をこうしたいから、こういう価値や機能とかサービスを作るんだ。だから、事業をこうしたいという、外向きの感じ、事業向けの矢印はイメージしやすいんですけど。
中から事業とか、足元、どう戦略、戦術を考えていくんだという、そこの矢印の接続が、私の中でまだ結構難しくて。既存事業で、そこにあるものを伸ばしていくんだ、みたいな発想でいくと、まだイメージが湧くんですけど、何か新しいものに変えていくんだという風になったときに、外になかなか、アンテナを持てていない人間が、どう、そこに接続していくんだ、みたいなところは、ヒントがあったらお聞きしたいです。
Mさんの会社のケースでいうと:風土的に内向きから事業が生まれてきた会社
これはですね、私は、Mさんが勤めている会社の社名も知っていますが、この場ではその固有名詞は出さないんですけど、でも、私の知っている御社は、むしろ内側から始まっているとか、内側をすごい大事にしている人たちだから、会社としてそのDNAがあると思うんですよね。いかに若い人たちを輝かせるかみたいな発想を持って、事業を作ってきている感じがすごいする会社ですし。
で、実際問題、その卒業生たちの社長もいっぱいいるじゃないですか。中でも、結構何人かは、やはり、とにかく人を輝かしたいと思って事業を作っていて、その先輩たちの生き様から学べることは、いくらでもあるんじゃないかなって思います。

確かに、まあ、カルチャー的にはそうですね。いや、確かに。いや、確かにそうですね。そうか、まあ、別に自分でそこが出てこなくてもいいわけですものね。事業に対して「こうした方がいいんじゃないか」とかも、言ってしまえば。振り返ると、割とそうやって、やってきたなっていう感じはしますね。
とはいえ、多少何か変えなきゃいけないときは、組織の中の知恵とか、なんか誰かが、それこそ外向いている人の何でそれやりたいのみたいなところのヒントを得たりとか。うん、なんか、確かにそういうことをしていた気がしますし、なんか、それで突破してきた気もします。自分で何とかしよう、というのがすごい強かったのかもしれないですね、急にそこに関しては。
特徴で言うと、本当にMさんのいる会社は、もちろん金儲けのためにとか、事業を作りたいとか、社会を良くしたいとか、外向きの人もいっぱいいますけど、この「一緒に働いている仲間を幸せにしたい」みたいな人も、すっごいいっぱいいる会社じゃないですか。すごいそう思いますから、自分が外向きのモチベーションで頑張るのか、内向きのモチベーションで頑張るのかは、別にどっちでもいいと思います。
これからの時代のマネジメントに求められることは

2~3年前に事業部長が変わったんです。それより前は、組織のこととか大事にしてそうな感じの人が、ずっと事業部長を長らくやっていたのが、2年ぐらい前に変わって。で、その交代は、下から見ていても、明らかにそのやり方では良くないから変えられたんだろうなという、交代の仕方だったんですよね。その新しくきた事業部長は、経歴といい、たぶん3~4年前からそういうなることを見据えて育成されてきた人なんだなと、なんとなく思っていました。
で、なんか、その人がしきりに、まあ「変化だ」「変えなきゃいけない」とかっていうことを、ずっと、仰っていて。急に組織や人の話が、社内的に本当になくなったんですよね。そこで、なんか自分自身が、っちにあまりベクトルを向けられなくなっていたというのもあるのかもしれないですね。これは振り返ると思うことですけど。
今のMさんから聞いた範囲の、切り取りの情報でしかないですけど、もう本当に、私もクライアントさんが何社かあって、一緒にいろいろなことを考えてきているときに、時代の転換点というか、もうビジネスマーケット的に、本当に結構大変なんですよ。これから、どうやって稼ぐのか?というのは、時代的にも一層大変なんです。
仮に組織や社員を守りたかったとしても、とにかく変化に対応できなかったら、あっという間に倒産します。だから、とにかく変化に対応できるとか、変化をリードできるという感覚で仕事をしてほしいというふうに、株主や、まあ株主以上に経営陣が思うのは、すごく、すごく分かります。
メッセージとして、「変われ」「今まで通りじゃ、もう通用しないぞ。食っていけないよ」と。経営者だって、積極的に社員の首を切りたいわけじゃないから、「このフィールドを活用して変化してほしい」という気持ちに経営者がなるのは、私はすごい分かる気がします。

話を聞けば聞くほど、なんか、(自分の考えは)甘いのだなという……あの、はい。なんか、その、反省と、恥ずかしさと、まあ一方で、35年間これで生きてきているので、なかなか、そうそう変わらないぞというのと。
けど、今のままの自分でいることは、それはあまり生き方としていいなとは別に思わないので、みたいな、いろんな要素が今、同時に、こう、襲ってきている感じですね。
もし自分のキャリアとして部長・経営陣クラスを目指していくのであれば
- 一般的に、部長・経営層クラスには、「自分のために」を超えて、部下やメンバーのために、会社のために、さらには会社の外、社会のことも考えて自ら働きかけていけることが求められます
- さらに今は、AIの進化など変化が激しく、ビジネス環境は年々難しくなっているため、経営層により近い層ほど、変化に対応できる力、変化に対してリードできるような視座が求められます