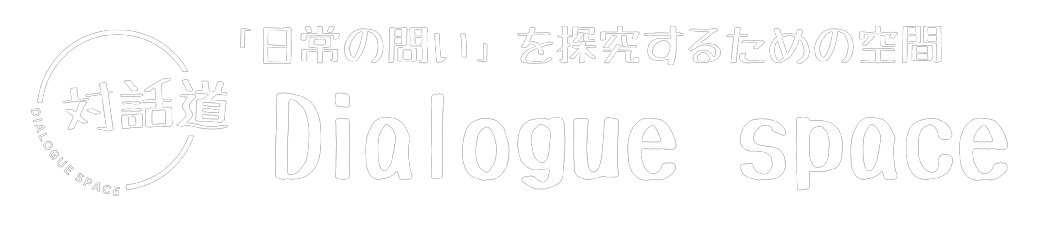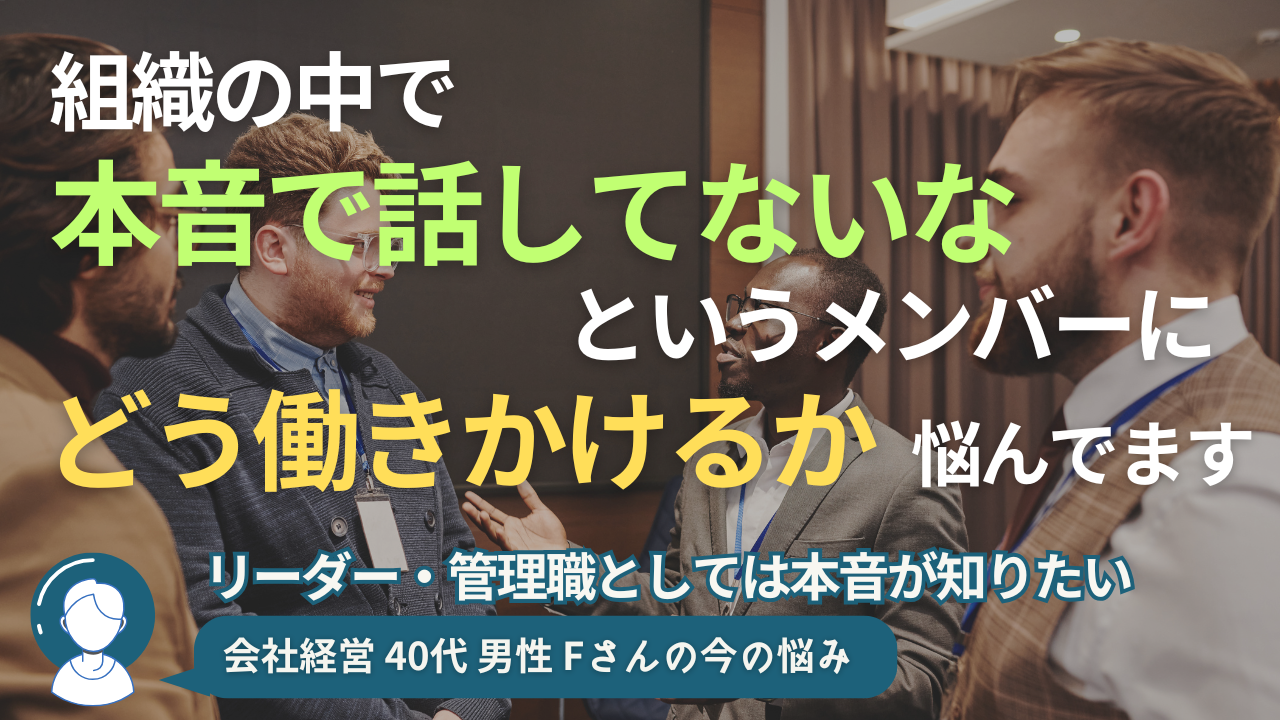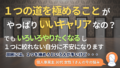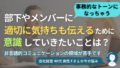動画で見る
記事で読む
組織の中で本音で話していないなという人への接し方

石川さんは、いろいろな会社にいって、組織内の、従業員同士の対話(コミュニケーション)を促すような仕事されてるわけじゃないですか。そのときに、社員同士が話しているのを見ていて、「この人全然本音で話してないな」みたいな人って絶対いると思うんですけど、いますか?
います、います。

そういう人に対しては、別に特に介入せずにいるのか、それとも何か本音をちゃんと話してもらうように、インストラクションとかで工夫をされたりとかしているんですか?
今の質問は、ひとことでまず答えると、いろいろなケースがありますね。意識してるし、考えてるし、ケースバイケースだし、みたいな領域だと思います。ちょっと分かりやすく言語化していくと、本音を持ってるのに言わないでいるんだろうなという人と、まあ何も考えてないんだろうなという人がいます。
特に意見がないから話さない人
後者の時は、簡単に言うと割とほっとくというか、どちらかというと、そうじゃない人たち、例えば、その場に10人いて、1人何も考えてないんだろうなみたいな人がいたとしたら、残りの9人たちが火が付いて、すごい議論するようになって、それに触れて、「あ、自分も何か考えなきゃいけないんだな」みたいになってくみたいなことがあったり。反対に、ちょっとこんな前向きな集団ちょっと自分は無理、もっと楽なとこに転職しようみたいになるとか。
どちらかというと、その人に直接アプローチするというよりは、残りの9人が変化していくことによって必然的に生じるものがあるという感覚が多いですね。
本音を持っているけど言わない人
逆に、この人は本音持ってるんだけど、言わないとか言えないって思ってるんだなみたいな状況のときは、その人が組織が良くなる鍵を1つ握っているみたいなケースが多いなと捉えています。
この場合は、もうこれは本当、あの手この手で、本音を話してもらえるように考えます。その人がちゃんと「じゃあ、言いますけど……」とか言って、「こうでこうで、こう思うんですよ」みたいなのを言っていただけるように、何かしらいろいろします。
何かしらいろいろしますというのは、すごいストレートな入りで、「Aさん、何かご意見ありますか?」みたいに、言ってみるケースもありますし、そうではなくて、何か「AやBやCやのメリットデメリットを、とりあえず一旦全員で書きましょう」とかというだけで、意外とそれを丁寧にやるだけで本音を書いてくれることもあります。「え、絶対だってここがダメで、ここがダメで、ここがダメですよね」みたいなのがバシッと貼られるみたいなケースもあったりとかするわけなんですけど、それは本当にケースバイケースですね。
何も考えていない人と本音はあるけど言わない人を見極める方法は?

この人は何か考えてるけど、言い出せないだけだというパターンと、何も考えてないパターンって、どう見分けるんですか? 感覚的なものなんですか? それとも何か質問して、○○と返ってきたら何か考えてそうだな、みたいなのがあったりとかするんですか?
逆質問みたいになってしまって申し訳ないですけど、例えば、飲み会などで4~5人とかで飲んでたとして、何か2人でわーって盛り上がってる話があったときに、後の3人は、ちょっとこう聞いてるモードじゃないですか。

そのときに、この人は「喋ってるのは別の2人だけど、この話題に関心があるんだな」というのと、この人は、「この話題に対して、どうでもいい、興味がない。何なら早く終わんねえかなこの話題という気持ちで黙ってるんだな」みたいなのって見てて分かりませんか。

そういう意味で言うと、僕はちゃんとそこを観察してなくて、そういう場になったら、全員共通の話題は何かな?と、話題を変えることを考え始めますね。飲み会の場合は。
だからち、この人はこの話に興味があるのかないのかまでは、顔色を見て見てないですね。今の話聞くと、そうやって人を見てんだなというのはちょっと今、分かりました。
そうですね、そこはかなり意識してると思います。

そうかぁ。僕な、なんかみんなでできる話題を話そうぜって思います。
みんなでできる話題話そうぜは、選択肢の1つなんですけど、でも例えばですね、企業向けなので、「みんなで、うちの会社が5年後にどんな会社になっていたらいいか考えましょう」という話をしたとき、これはみんなで話せる話題なんですよ。だけど、興味ない顔する人もいるんです。

なるほど、それはそうだな、分かりました。
Fさんは、非言語の観察力はより意識したらいいかもしれないですね。言語に頼りすぎない。

そうですね。
個別面談や全体ミーティングであまり話さない気になるメンバーがいる

より具体的な話をすると、私の会社では、私がメンバーの方に、半年に1回個人面談してるんです。ですけど、本音を話すのが苦手でみたいな人がいて、全体ミーティングのときもあんまり発言しないので、どうしたらいいんだろうかなというのがまず1つあった感じなんです。
差し支えない範囲で、どんなやり取りしてるのかとか、どんな方なのかとかちょっと教えていただいていいですか?

これは見た印象ではあるんですけど、その人と私は、従業員と雇用関係にあるので、そこを上下関係と見てるんだろうなという感じがあります、こちらから見ると。そして、できる限りここの上下関係というのを緩和するような声かけをしてるつもりではあるんですけど、本人の中で「いや、そもそも本音で喋ること自体が抵抗があるんですよね」って個人面談のときに言ってらしたりして。そこで、もしかしたらね、「本音喋るのが苦手なんです」って言ってくれてる時点でも自己開示してくれてるのかもしれないんですけど。
それも含めてこっちとしては「いや、まあ全然話してくれていいんですよ」という声がけはしてるけれども、やっぱり全体ミーティングの時とかでもあんまり発言がなく、これは何か僕がもうちょっとサポートしてあげた方がいいんだろうかとか、それともこのままの方が彼女にとっては居心地がいいんだろうかとか、そういうことをちょっと考えてるという状況ですね。
まず、1対1の場面というのと、複数人の場面でというのは、その方にとってはかなり違うはずだと思います。というより、自分だったら全然違う場として捉えます。
1対1のところでは何かいろいろ話したりしてくれるんだけども、全体の場では言わないみたいなのも全然あり得ることです。まずはそこを目指すなら目指したらいいかなというのはあって、全体の場と個人面談を一緒に考えない方がいいと思います。
いくつかあるんですけど、1対1のコミュニケーションにフォーカスした時に、まず「本音で喋るの苦手で」と確かにそれを言ってくれてる時点で結構自己開示してくれてる感じはあります。
ただ、それ以上は実際「苦手なんで」って言ってるので、特段どんな気持ちでいるのかとか、どんな意見でいるのかとか聞いてもあんまり出てこないとしたときに、相手を尊重するという手もある中で、「私はもっと話しやすい関係性を作っていきたいと思っています」というのは、Fさんのニーズなんですよね。
私はあなたとそういう関係を作っていきたいということなので、別に相手が、Fさんと本音で話していきたいと、望んでるわけじゃない。まずそこがすごい大事な話だなと思います。
なので、「私はあなたともうちょっと踏み込んだ関係性を作っていきたいと思っております」というのをちゃんと伝えていったらいいと思いますし、それでいうと、それこそ自分のニーズをわかってもらうよりも、まずは相手の苦手で言ってる気持ちを、一旦受け止めたりしたりした方が、よっぽど関係性は深まりやすいのかなみたいな気もしたりします。

そうですよね。
これもやっぱり仮に本音で喋ってもらうにしても、もう結構時間をかけていくものなのかなって思ってるんですけど、尊重しつつこちらのお気持ちもちょこちょこ伝えつつみたいなイメージでいいんですかね?
どう捉えるかなんですけど、私がFさんの立場だったら、まあ長いお付き合いになるだろうし、長いお付き合いにしたいし、良い関係を築いていきたいしと自分の方が思っているときに、焦らずじっくり関係性を作っていくのがいいかなと考えると思います。
それで、気付けば3年もしたら、随分自分のことは信頼して喋ってくれるようになったなとか、周りの先生方とも、前と比べると随分コミュニケーションを取って、とにかく喧嘩しないようにぶつからないように、本音を飲み込んでとかではなく、楽しくお話ができている関係性が随分できるようになったなと、なっていくイメージも持てるからです。そんな関わり方でいいんじゃないかなという感じなんですけど、それを聞いてFさん的にはどうでしょうか。
本音を隠したまま突然辞めますとなるのが経営者としては困る

結構、今の状況からすると1番リスキーだと思うのは、本音を隠したまま、ある日突然その方がやめますとなったときに、こちらとしては、また新しい人探さなきゃいけないし……とか、そういうことを考えると、できる限り色々話し合える関係性を構築しときたいなっていうのがあります。今のままだと、そういう可能性があるのかどうかもわからないんですよね。
なので、もちろん本音で話せることが早いに越したことはないんですけど、その方がやめないのであれば、石川さんが言ってたように、3年とか5年とか長い目で見ていうのも、それはそれでアリなのかなみたいな感じですね。ちょっと答えになってるかわかんないですけど。
今思ったことは、2つあります。
1つは「私はこう思っているんです」という自己開示をちゃんとできるかどうかです。
これは間違いなくこちらの都合の話なので、「これはあなたのため」と格好つけて言ったりせず、「あなたが本当は不満なのに、不満なことを私に言えないでいると、私にとって損失とかリスクがあるので、私としては本音が言える関係性が築けると良いと思っています。もうこれは、自分のためでございます。」いう話を、ちゃんと自己開示できるかどうかは大事だと思っています。
その方は、そのくらい大事なメンバーなのであれば、まずその評価をちゃんと伝えた方がいいと思います。あなたは先生として素晴らしくて、うちの戦力で、長く続けて欲しいって思っていて、だから、経営者の立場としては、もし不満が溜まってやめられちゃったりすると困るんです。本当に、貴重な戦力だと思っています、というある種の評価を伝えるということです。
もう1つは、やっぱり言語化するのが苦手な人がいたときに、こちらで観察して、代弁してあげたり、気付いて配慮するというのも大事であるということです。
例えば、その先生の生徒さんが10人いたとして、「他の9人に対してはこういう感じの接し方しているけど、ちょっとこの生徒さんは苦手なのか、ちょっと微妙に接し方が違うような気がしてる」みたいなことがあったときに、それに観察して気づいて伝えてみると、その先生が急に「実はちょっとその生徒さんについては悩んでいて…」と話し始める……みたいなこともあるかもしれません。
向こうから言ってくれなくても、観察していたら気づけるものもあるわけですよね。

ちゃんとどれだけ観察してるかという言語コミュニケーションだ。うーん、そうですね。いやおっしゃる通りですね。だから、こっちも自己開示してなかったってことですよね。そういう意味で言うと、自己開示してないし観察もできてないし。なるほど。いやあ、自分ではなかなか気づかんものですね。自己開示してるつもりだけどあ、そう言われてみれば、そこのところは開示してなかったわ、みたいな。
分かりました。ちょっと次回の個人面談のときに、個人面談のときじゃなくてもいいけど、普段から戦力であるということを伝えつつ、個人面談のときに「突然やめられると困るんですよね」みたいな話もしつつ、非言語コミュニケーションしつつ、、言語化をお手伝いし……なるほど!ちょっとやってみます。
組織の中で「本音で話してない」人にどう接していけばいいのか
- 組織の中に本音で話してない人がいたときに、「本音があるけど話していないのか」「意見などが本当に特にないのか」は、よく観察したりして見分ける必要がある
- 今回のケースでいえば、「本音で話してほしい」はこちらのニーズであることを忘れない
⇒こちらからまず自己開示をする
⇒ゆっくり信頼関係を育めるよう努力する
⇒言語化が苦手な人には非言語的コミュニケーションもより大事に接するなど、ケースによってさまざまな考え方がある